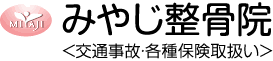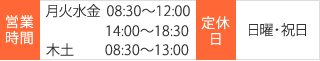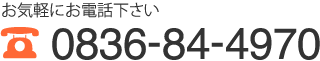初秋に感じるだるさや疲れは、「秋バテ」のせいかもしれません。
今回は、夏バテしなかった人ほど注意してほしい
秋バテ対策について解説していきます。
夏バテしなかった人ほど「秋バテ」に要注意!
「暑さ寒さも彼岸まで」と言われますが、近年は彼岸を過ぎても、
夏のように暑い日もあります。
さらに、9月は季節の変わり目によるストレスも多く、
体調を崩しやすくもなります。
そんな時季に気をつけたいのが、「秋バテ」です。
夏は勢いで乗り越えられても、急に涼しくなる初秋になって、
疲れや不調が現れてしまうのが秋バテです。
秋バテを引き起こす要因には、次のようなものがあります。
1. 長引く暑さの影響で、疲れを抱えたまま秋に突入
9月は、夏のような猛暑の日もあります。
暑さはそれだけで体への大きなストレスになりますし、
夜の寝苦しさも続く場合、良質の睡眠をとりにくく、
疲れが解消されにくくなります。
2. 夏の生活習慣が抜けきらず、体の負担は増える
暑さは、気分を解放的にさせますし、9月には夏休みをとる人も多く、
9月に入っても夏気分が抜けず、夜遊びや暴飲暴食、アクティブな
レジャーなどで、体に負担を掛け過ぎてしまうことがあります。
冷えたお酒を飲む、焼き肉などの消化に悪いものを食べる、
薄着のままで夜を過ごす、1日中遊びまわる、といった生活習慣が続くと、
胃腸の疲れや冷え、体力の消耗によって、体はダメージを受けてしまいます。
3. 朝晩、日ごとの激しい気温差
9月に入ると、1日の気温差が10度近くになる日もあります。
すると、日中は半袖、夜は上着が必要になるくらい、
寒暖差が激しくなることもあります。
また、9月は日ごとの気温差も激しく、真夏日に近い日があれば、
晩秋に近い日もあるなど、安定しません。
こうした急激な寒暖差によって自律神経のバランスが
乱れると、体調を崩しやすくなってしまいます。
4. 気圧と気候の変動による影響
9月は長雨や台風が多く、気圧が変動しやすい時季です。
変動する気候に体が適応できなくなると、自律神経の
バランスが乱れ、頭痛やめまい、だるさ、肩こりなどの
体調不良を感じやすくなります。
「秋バテ」予防・軽減に試したい3つのコツ!
「秋バテ」を防ぎ、軽くするには、体をいたわる、無理をしない、
ゆっくり休むといった生活習慣を心がけることが大切です。
まだ秋バテしていない人も、既にそうなってしまった人も、
9月には次のような生活習慣を心がけましょう。
1. 体を温めるスープがおすすめ、お酒を飲む場合は常温で
体をいたわるには、体を冷やさず、体の中から温めることが肝心です。
冷たい飲み物や消化に悪い食事で弱りがちな胃腸の調子を整えるためにも、
体を温め、胃腸に負担の少ない食べ物をとるようにしましょう。
なかでも、スープはおすすめです。
ビタミン、ミネラル豊富な野菜をやわらかく煮込んだスープや、
疲労を回復させるビタミンB1がたっぷり含まれる豚汁などで、
体をいたわりながらしっかりと栄養補給しましょう。
また、この季節にお酒を飲む場合、常温や温めたお酒を
少し嗜む程度にしましょう。
ただし、疲れているときには、お酒を控えるか、
グラス1杯程度にしておきましょう。
2. 衣服や入浴で体を温める
9月はまだ暑いからと油断して、薄着のままで過ごさないようにしましょう。
日中は半そでいられても、夕方から夜にかけて気温はガクンと下がります。
いくら暑くても、ノースリーブ、素足にサンダルなどの格好は、
9月に入ったら控えた方が無難です。
外出時には、着脱しやすいカーディガンを携帯し、
ストッキングか靴下を履くようにしましょう。
また、入浴をシャワーのみで過ごしている人は、できるだけ
湯船に浸かって、体を温めましょう。
朝方がいちばん冷えるため、就寝時には長袖のパジャマを
着るようにしましょう。
3. アクティブな予定を入れず、しっかり休む
初秋は、体を秋の気候に適応させていく移行期です。
体調が崩れやすいため、予定を入れすぎて、体に負担を
かけないようにしましょう。
特に週末には疲れが出やすいので、体を休める時間を
増やすことが大切です。
家事やレジャーを頑張らず、ひたすらのんびりと過ごす
時間を楽しみましょう。
ただし、生活リズムを保てるように、起床、就寝、食事の時間を
一定にする、服を着替える(1日中パジャマで過ごさない)、
最低限の身づくろいをする、といったことを心がけましょう。
天候変化によるストレスを甘く見ずに対策を!
秋バテ対策は体をいたわり、ゆっくりと過ごしながら、
体調の自然な回復を待つのがポイントです。
季節の変わり目の気候や気圧の変化は、心身にとっては
かなり大きなストレスになります。
特に、日頃ストレスを抱えている人は、この時期に
体の負担を倍増させないよう、無理のない生活を
心がけてみてください。