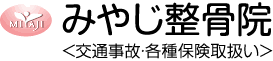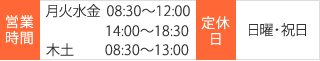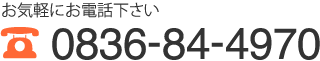指先を使う動作は、脳の「前頭連合野」という部分を刺激するため、
認知症予防に有効と考えられています。
子供の頃は、学校授業の体育や部活動がありましたが、
大人になり年齢を重ねると体を動かす機会は減っていきます。
そのため、手や指先を使う運動やスポーツを取り入れて、
心身の健康維持に役立て元気に長生きしましょう。
運動によるメリットは数多く挙げられますが、米国疾病
予防管理センターによると、運動が心身にもたらす
メリットについてこのように説明しています。
■運動の直接的な健康効果・メリット
・運動によって消費されるカロリーが食事などからとる摂取カロリーを
上回れば「カロリー負債」となり体重減少に貢献する
・体重コントロールを可能にするためには継続的な運動習慣が必要
■運動の間接的な健康効果・メリット
・高血圧による病気のリスクを減少させる
・2型糖尿病、心臓疾患、がんなどのリスクを減少させる
・関節痛やそれに関連する歩行困難などのリスクを減少させる
・骨粗鬆症とそれに伴う転倒のリスクを減少させる
・抑うつ状態の改善
運動によって期待できることとして、「生活習慣病の予防」
「脂肪が燃焼しやすい体づくり」「若々しい心身の維持」
「脳の活性化」などが挙げられます。
とりわけ、手や指先を使う動作を行うと脳の活性化につながり、
認知症などの予防や改善にも効果が期待できると言われています。
指先を使う動作が認知症予防に有効
人間は手や指先を使うことで、脳の「前頭連合野」という部分を
より活発に働かせることができます。
「前頭連合野」は、巧みな動作を可能にし、思考・意欲・情動
などを実際の行動に変換する場所です。
例えば、手を使ってある動作を行う場合、「前頭連合野」から
脳の中央にある「運動野」に指令が届き、そこが手の筋肉や
関節を動かすことによって実際の行動に反映されるようになります。
手をよく使えば使うほど、手から脳へ送られる信号が増え、
それを受け取った脳とその信号をつなぐ神経回路である
シナプスの働きが活発になるため、こうした動作を繰り返す
うちに脳がより活性化されると考えられています。
手はものを握ったり離したりして巧みな動作を行いますが、
指先を使う動作には、小さなものをつまむピンチ動作、
指先を触れて動作を行うタッピング動作、指を何かに
ひっかけるフック動作などがあります。
また手のひら全体を使って行う動作としては、重いものや
硬いものなどをしっかりと握るグリップ動作などがあります。
特に指先を使って動くピンチ動作やタッピング動作、フック動作などは
脳の機能障害でのリハビリテーションや認知症予防などに
効果が期待できるものとして注目されています。
運動やスポーツなどにおいても道具を使って行うものは、
手の動作が鍵となることが多く、このことからも運動やスポーツは
認知症予防にもつながるのではないかと考えられます。
指先を使うおすすめの運動・スポーツ
手や指先をなるべく動かそうと思っても、面白くなくては、
なかなか続かないものです。
手のひら全体を使って行うグリップ動作は「ものを握る」ことであり、
道具を使ったスポーツであればこの動作を伴うものがほとんどです。
テニスやバドミントンなどのラケットを握ったり、ボールを握って
投げたりといったことがその例として挙げられます。
また野球やソフトボールのような比較的小さなボールは握る動作で
指先にまで力が入り、グリップ動作とともにフック動作も加わります。
他にもタオルを使ったタオルストレッチなども
グリップ動作を伴う運動の一つと言えるでしょう。
一方、より細かな動作が求められる指先の動きとして、
スポーツに当てはめてみるとピンチ動作においては
指先でつまんで投げるダーツが挙げられます。
またフック動作を伴うものとしては壁の突起物に手や指先を
引っかけて登るボルダリングや、ボールの穴に指を
引っかけて投げるボウリングなどが挙げられます。
目的にあわせて、様々な運動の選択肢がありますが、
脳の神経回路をより活発に働かせたいと思う方は、
手や指先を使った運動などもぜひ取り入れてみてください。